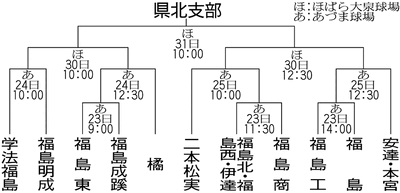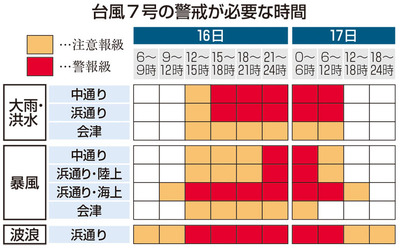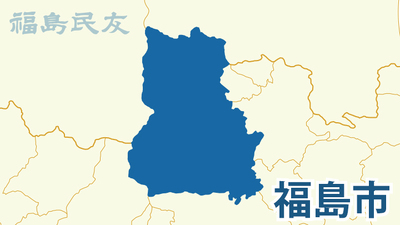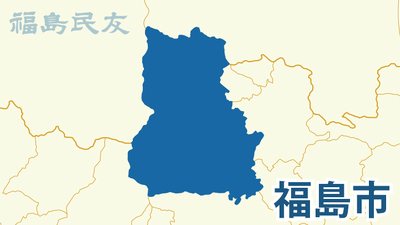今期夏ドラマでは偶然にも“シングルファザー”が題材となったドラマが2本、放送されている。月9『海のはじまり』(フジテレビ系)と火10『西園寺さんは家事をしない』(TBS系)だ。どちらも子役は“娘”であり、母親が病死、現在の相手役は年上、外部を巻き込んで家族としての関係性をどう築くか…という大枠にも共通点が見られる。ドラマにおける父子家庭のフォーマットは、以前から鉄板コンテンツとして描かれてきた。だが現代ではより描き方が繊細に。センシティブな部分も臆さず描写する変化が見て取れる。改めて父子家庭ドラマの歴史や変化について振り返る。
【写真】令和の父子ドラマを象徴するワンシーン、ドライヤーで泉谷星奈の長い髪を乾かし、あたふたする目黒連
■「不器用な父」と「可愛い娘」で描かれてきた父子家庭フォーマット
父子家庭ドラマの傑作といえば、多くの人が『北の国から』(フジテレビ系)を頭に浮かべるだろう。81年より連続ドラマとしてスタートし、その後も2000年代までスペシャルドラマとして放送。東京から故郷の北海道へと戻り、大自然の中で暮らす父子とその成長が描かれた名作だ。
故・田中邦衛さんが演じた黒板五郎は決して頼りがいのある父親像ではない。特に初期は外で面白くないことがあれば子どもに当たるなど内弁慶であり、そして情けなくもあり…。それでも悪戦苦闘しながら家族を守り、子どもたちが巣立ってからも抱えた問題について不器用ながらに向き合う姿は感動的だった。
その後も82年に西田敏行主演の『池中玄太80キロ』(日本テレビ系)、92年に柴田恭兵、三浦洋一、風間トオルが出演した『子どもが寝たあとで』(日本テレビ系)が放送。80年代~90年代ドラマにおける父子家庭ドラマのフォーマットは「不器用な父」が家事・育児にいかに奮闘していくかコメディと感動が絶妙な配分で描かれていた。ドラマならでは(!?)ともいえる「いきなり父になる」という起承転結の「起」から始まり、家事・育児の0からスタート、外では威厳のある男性でも家に帰ったらダメダメのギャップをコミカルに。
当時、リアルでは育児の担い手の大半が女性であった。「24時間戦えますか」というCMのキャッチコピーにも反映されているように男性は仕事に奮闘。仕事はフォーカスされるが、家庭育児という面では自由気ままに暮らすステレオタイプであったため、家庭を顧みなかった分、子への対応に男性が困り苦戦する姿は滑稽であり、そこから生まれるさまざまな葛藤と克服、失敗、成長など視聴者にとってはそれだけでも面白いエピソードになり得ていた。
■スタイリッシュなパパ像を築きあげた田村正和、2000年代以降も多様な父子関係が描かれヒット作を量産
そんな中、父親の描かれ方として、人間味のある描き方から“パパ”と呼ばれるにふさわしい、スタイリッシュさを持ち合わせたパパ像が現れてきた。これを提示したのが故・田村正和さんだ。『パパはニュースキャスター』(1987年、TBS系)、『パパは年中苦労する』(1988年、TBS系)はどちらも人気を博し、プレイボーイのパパが子どもたちには振り回される滑稽さ、育児に奮闘して父親として人間的成長をしていく姿が視聴者のハートを鷲掴みに。
さらに『パパとなっちゃん』(1991年、TBS系)では20歳の娘を小泉今日子が好演。パパは娘を溺愛、娘はパパのダメなところも含めて受け入れるという器の広さで、恋人同士とはまた違う、広い意味での“愛しい”世界観が甘くもあり切なくもあり、いまだに記憶に残っているという方々もいるだろう。
「この流れを踏襲しつつ近年では“娘役”を起点に、さらに多角的な父子関係が描かれました」と話すのはメディア研究家の衣輪晋一氏。
血のつながりがない、父子関係にない人が父親になるパターン(『マルモのおきて』(2011年、フジテレビ系)、映画『うさぎドロップ』(2011年)。また、第三者の力により壊れた家族関係を修復、父親の役割が問われる『家政婦のミタ』(2011年、日本テレビ系)や、父親が娘の家庭を上手く回せるようサポートに徹している『監察医 朝顔』(2019年、フジテレビ系)など、その時代の世情を反映したパターンもある。
「父親と娘の設定が多いのは、娘という、異性である父親からすると圧倒的に分かり合えない存在と対峙する過程をいかに描くかで、物語に様々なバリエーションが生まれるから。外ではバリバリにやっていた男性が娘の前ではダメダメになる。自分とは別の性だからこそ、気持ちが分からない、気軽に触れられない葛藤。だからこそ子への愛情をどう伝えるか。分かり合えなかった両者が分かり合えたときの感動、家事・育児・人間的な部分の成長など様々な視点からストーリーをとらえることができる強みがあるからでしょう」(衣輪氏)
■事細かに描写される“パパしぐさ”、経験値のないドタバタ劇ではもはや共感されない!?
これまでの父子家庭ドラマは、“不器用な父”という描き方が、心情としても、行動としても強調して描かれてきた。だが令和のいま、夫婦二馬力で働くのが当たり前で、男性が家事育児をこなすことも当たり前に。「不器用で家事育児も経験値ありません、という0からスタートでは、まったく視聴者に共感されない時代になっているのかもしれません」と衣輪氏。
では今期の『西園寺~』と『海のはじまり』について見てみよう。共通点は子役が両方とも“娘”、母親と死別している、父親の相手役として年上女性が登場する。さらに「パパしぐさが強調して表現されている」と同氏は指摘する。
まず『西園寺~』では、松村北斗が家事育児を完璧にこなすパパを演じている。その中から切り取ると娘が牛乳をこぼしてしまったシーン。ここでは牛乳の海から救出してはやく現状復帰しなければとアタフタする中で、松村が娘を抱き上げ、移動する前に足の裏を確認する動作が入っている。これはもしかしたら牛乳を踏んで移動させた先で二次被害が生まれないかを危惧する配慮であり、松村はこの“育児経験者”の細かい芝居を見事に表現していた。「ほかにも、単体で動くときはベビーカーのストッパーを止めてから移動するなど。育児あるあるの行動だが、その解像度が高い」(衣輪氏)
次に目黒連が父親役の『海のはじまり』。母親が死ぬまで娘の存在さえ知らされていなかったので娘の関わり方に困惑する描写もあるが、これまでと構造が異なると感じたのは、“できる男性”を登場させているということ。池松壮亮が亡くなった母親の同僚役で、まさに父親のような接し方で娘とコミュニケーションを取っている。娘の髪の毛を扱い慣れている池松の芝居、頑張って三つ編みや編み込みをしようと奮闘する実の父役の目黒の芝居は対照的であり、この比較だけ取っても強いドラマ性がある。
昭和・平成の父子ドラマであれば、父が娘の髪の毛を上手くゆえない→ぐちゃぐちゃの髪のまま登園→怒る娘→終盤ではちゃんとゆえるようになっていて…という描写にとどめられていたであろう。また不器用な父・経験値のない父の成長を真正面から描くことでそれがコメディにも感動にもフィットし、カテゴライズされた“父子もの”としてステレオタイプに描かれていたと思われる。
「ですが今の時代、それでは通用しなくなっている。父子の描き方が難しくなっていると言えるのかもしれない。男性が全面的に家庭をまわす視点があることが前提となり、俳優の何気ないしぐさをとっても、緻密な描き方がなされている。その繊細さが視聴者の共感にもつながっていると言えるでしょう」(衣輪氏)
ステップファミリーとしていかに家族を築くか、相手女性の視点も入っていることにも変化が見られる。これまでのドラマは、子どものことを考えて恋人がいても、立ち止まることが定説だった。だが両ドラマには、父子の関係性に入り込む女性の葛藤も描写されている。つまり“父子関係”から“家族のかたち”を追求するのが、ドラマ後半にむけてのストーリーの要になっていきそうだ。
家事・仕事の分担、共働き家庭における考え方のアップデートが行われた今だからこその今期の父子家庭ドラマであり、父子とその周囲の関係性をより一歩踏み込んだかたちで描くことに成功している。令和の“父子ドラマ”がどのような令和的ラストを迎えるのか。制作者たちの手腕に期待する。
(文・西島亨)
「父子家庭」ドラマ、描き方に変化 “不器用なパパ”の奮闘劇では共感されない時代に?
08/20 12:18
- エンタメ総合