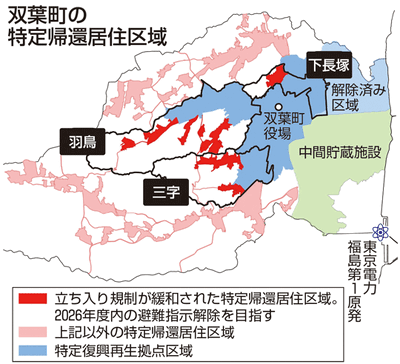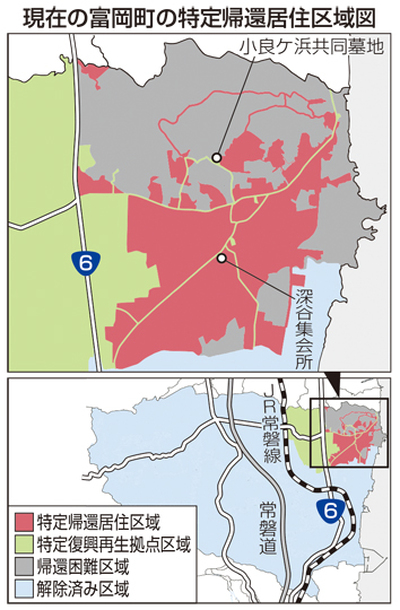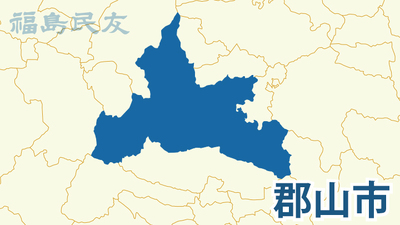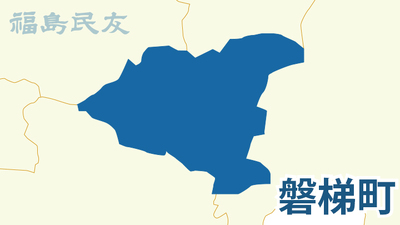東京都内で17日開かれた映画「Fukushima 50(フクシマフィフティ)」の撮影終了会見。佐藤浩市さんと渡辺謙さんは「福島出身の名もなき作業員が、家族や故郷のため、死を覚悟して事故対応に挑んだ物語である」と強調した。作品の海外展開も視野に入れており、日本映画界を代表する2人が「福島の記憶」の発信役を担う。
「まだ終わっていないどころか、始まっていないのかもしれない。当時を振り返りつつ前を向くために何をすべきか皆さんに考えてもらいたい」。
主役の佐藤さんは福島への思いを語り、映画を通して「われわれがメッセンジャーになる」と覚悟を示した。
渡辺さんは被災地の悩みを理解しているからこそ、これまで福島を題材にしたエンターテインメントに関わることに抵抗感を抱いていた。
作品の内容を知り「僕たちが力を発揮できる映画で現状を知ってもらいたい」と考えが変化。「時間はかかってしまったが、そういう作品を届けることができると、福島の皆さんに言いたい」と打ち明けた。
水上繁雄プロデューサー・KADOKAWA映画企画部長は「世界に類を見ない震災と原発事故の内部を描き、後世に伝え、世界に発信したい」と語った。作品はエキストラ約2200人が参加し大規模セットで撮影。椿宜和プロデューサーは「震災当時を思いながらの撮影で、現場は緊張感が漂った」と振り返った。
◆「何かを感じ取って」 当直長・伊崎利夫役の佐藤浩市さん
撮影セットが忠実に再現されていた。電源を落とした暗い中での撮影が進む中、出演者みんながやつれていきリアルに感じた。
人間には忘れなければ生きていけないことと、絶対に忘れてはいけないことがある。映画で扱っている東日本大震災は後者。われわれがメッセンジャーとして事実をどう刻むか考えた。
震災を「まだ8年」「もう8年」と考えるのかはそれぞれある。映画を見る中で今の10代の子どもたちに何かを感じ取ってもらいたい。未来を生きる自分たちにとって何が必要なのかを含めて考えてほしい。
◆「忘れないでほしい」 第1原発所長・吉田昌郎役の渡辺謙さん
メディアで扱われることの多い所長の吉田昌郎さん役はプレッシャーだった。緊急対策室の外ですごいことが起きている焦燥感をどう感じるかも考えた。
非常に助けになったのは吉田さんの近くで実際に働いた方が撮影現場にみえたこと。メディアに映っていないときはどんな行動をしていたのかを根掘り葉掘り聞いて役を作った。
ここ数年、仕事で社会に関わることを自問自答してきた。きちんと役と向き合ったことで原点に戻った気がする。今後、福島の現実を忘れないでほしいということを問い掛けていきたい。