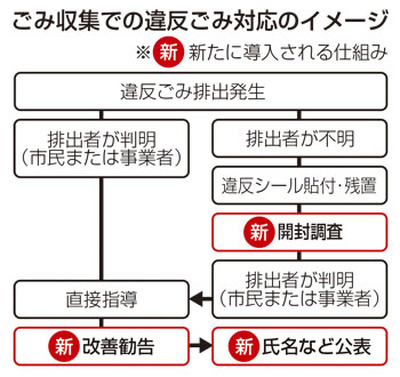仮設住宅の解消に15年要することを東京電力福島第1原発事故の特殊性のみに帰結せず、避難者の一日も早い生活再建のために何をすべきか考える必要がある。
県が、大熊、双葉両町向けの仮設住宅の無償提供を2026年3月末で終了する方針を決めた。4月1日現在、両町の避難者数の6%ほどに当たる約千人が、県内外の約600戸に入居している。大半が民間の賃貸物件を借り上げた「みなし仮設」だ。
県は両町の避難指示解除が進み、災害公営住宅の整備など、生活環境が整う見通しとなったことを踏まえ、終了を判断した。避難指示が出た他の市町村も同様の判断の下、順次、仮設住宅の解消が進められてきた。公平性の観点からも大熊、双葉の無償提供を終えるのはやむを得ない。
両町の避難者は家賃を支払って現在の住宅に住み続ける、あるいは転居するかの判断を迫られることになる。原発事故から13年余りたってなお、生活再建を促し切れていない国や県の責任は重い。
町域の大部分が帰還困難区域となった両町は、避難指示の解除や復興の取り組みが他の避難市町村と比べ遅れた。長期の避難生活で新たな生活基盤ができたことに加え、高齢化や健康不安など入居者の課題は複雑化している。
仮設住宅から次のステップへと円滑に踏み出せるよう、県には、両町や避難先の自治体と連携し、避難者の事情に応じた支援を提供することが求められる。
仮設住宅の解消を契機に考える必要があるのは、復旧・復興に関連する既存の法制度と避難者の現状とのずれだ。福島大の川崎興太教授(復興、都市計画・まちづくり)は、広域避難の必要性が薄い中規模の自然災害を念頭に置いて作られた枠組みが、原発事故に適用されている点を問題視する。
既存の枠組みで対応できる自然災害ならば、地域内にとどまった被災者が、復興事業などの経済的な波及効果を享受することが可能だ。一方、広域避難を強いる原発事故の場合は避難者が復興事業の効果を受けにくい上、不慣れな土地で生活を立て直す負担が伴う。
被災地に焦点を当てた制度の仕組み上、ハード面の復旧・復興に予算や人員が投下されやすく、避難者の生活再建支援が十分だったとは言い難い面がある。
仮設住宅を15年間提供しただけでは、住居支援の実績の積み上げにとどまる。長く避難生活を強いられている人たちが自立できるよう、国は制度と現状のずれを埋める手だてを講じるべきだ。